農業と研究一自分が興味を持つものは将来のある時点でつながる/博士後期課程3年 杉田恭将さん②
2025/06/30
農業の発展につながる金融工学の研究
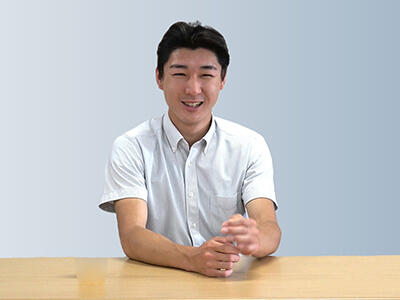
気象現象による損失をヘッジする金融商品として、天候デリバティブというものがあります。天候デリバティブとは天候という不確実性を有するものによるリスクを管理するもので、たとえば悪天候や気温変動の発生などの気象現象を取引する金融商品のことです。例えば、今月の10日から30日までどれくらい雨が降るかによって野菜の成長が変わってしまうとか、ぶどうなどの果物は収穫時期に雨が多すぎると裂果して被害が出たりします。こうした天候などの"不安定で不規則なもの"についての知見を得るべく、現在は力学系、特にカオス力学系の基礎的な理論について研究をしています。カオス力学系とは初期値にわずかな変化を与えると、はじめは似たような振る舞いをしていても、将来の挙動は大きく異なるようになるという特徴(初期値鋭敏性)があります。例えば、天候モデルに温度や湿度などの数値を入れたときに、気温などの観測誤差が0.001度くらいの微小でも、3日後、5日後と日を追うごとに誤差が大きなものに発展していくというものです。この研究が将来的に天候デリバティブとか農業の開発にも使えるのではないかなと考えています。農業は不安定性の高い、自然を相手にした仕事で、プロの農家であってもなかなか収益も安定しないといいます。今年の夏、どれくらい収穫できるか分からないといった不確実性から敬遠されて、第一次産業から手を引いてしまう、これが日本の現状ではないかと思います。金融工学の知識も使って、このようなリスクを少しでも補填するようなことができたらと挑戦しているところです。天候モデルはカオス性により設計が難しいという面もありますし、デリバティブ、金融工学的視点での研究に関しても追いついていない部分もありますが、今後の社会において必要とされる研究分野ではないかと思っています。モデルというのは100%当てはまるわけではないのですが、より精度を高く、より理論的に詰めて実現象に即したものへとブラッシュアップしていくことはできるかなという感触はあります。
学生の皆さんへ
学生の皆さんへお伝えしたいのは、学生時代に経験できることはしておいた方がいいということです。社会人になると仕事に追われて、身近で起きている社会問題について考える時間的な余裕がなくなるかも知れません。学生のうちに社会のさまざまなことに触れておくと、その経験が社会に出てから役立つんじゃないかなと強く感じています。何でもかんでもやればいいという訳ではありませんが、社会のなかで自分自身が少しでも興味がありそうなところに目を向けてみたらどうでしょうか。視察に行ったり、地域の方と交流して現場を見たり、いろいろ社会経験をさせてもらえる部分もあると思います。自分の興味関心があるなら何でもいいと思うので、そういったところに関係を持ってみるということが重要かなと思います。

大学院進学については、正直なところ研究に興味がなければやっていくのはなかなか難しいですが、自分の興味・関心で、知識は研究しながら身につけていくものでもあるので、知識がないから研究できないわけではありません。必要な知識は必要なたびに身につければいいのです。社会が抱えている何かしらの課題に直面した時に、それに関連する理論や応用的な学問はどのようなものであるかと学術的な立場から探っていくことができれば、その問題の解決の糸口になるんじゃないかなと思います。研究は社会に対してなんらかの形である程度還元されなければなりません。理論研究ももちろん重要ですが、実生活のさまざまな現象と関連付けたところで行う応用的な研究も同様に必要なものだと思います。その意味でも、さまざまな社会の問題、課題に触れてみるということが重要です。
私はこれから研究者、教育者の道を歩いて行こうと思っています。まだ26歳ですけれども、若手ということに甘んじていては、後進が育っていかないと思っています。日本の未来を担っていくのは、これからの世代です。日本の社会が活性化し、上手く回る方向にいくように、次世代を教育していくのは重要であり、大人の使命だと思うんですね。ですから私が成し遂げようとしている課題も教育から離れたところでは実現できないと思います。研究を通じて理論的な面で社会の役に立つということも大切ですが、それだけで満足するのではなく、新しい人材を生み出す"教育"という面でも社会に還元していきたいと考えています。


